お知らせ・ブログ NEWS / BLOG
- ブログ
- 2025.07.10
知らないでは済まされない:梅毒の初期症状と検査の必要性
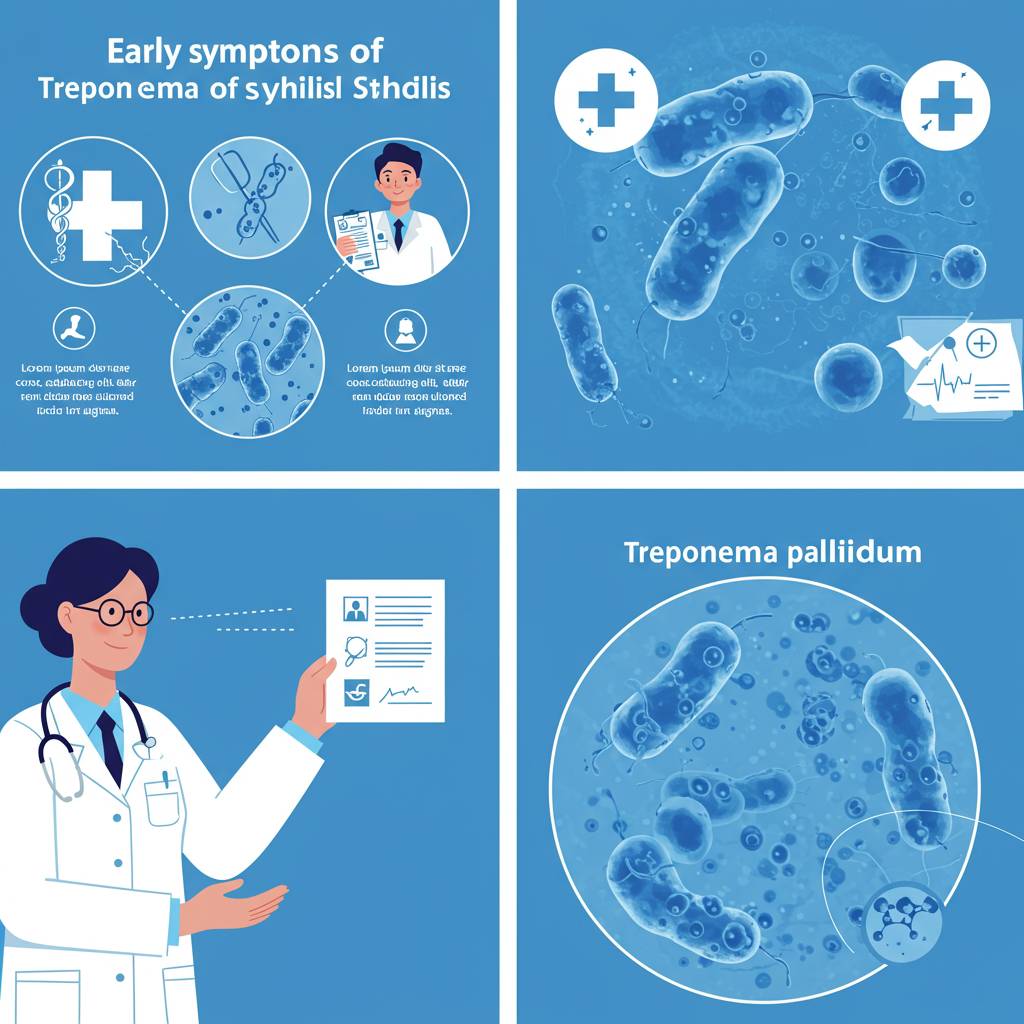
近年、日本全国で梅毒感染者数が急増しており、2023年には過去最高を記録しました。広島県内でも例外ではなく、感染の拡大が懸念されています。しかし、梅毒は初期症状が軽微であったり、症状が現れなかったりすることも多く、気づかないうちに進行してしまうケースが少なくありません。
梅毒は早期発見・早期治療が可能な性感染症ですが、適切な知識がなければ見逃してしまう可能性があります。皮膚の小さな発疹や痛みのないしこりなど、見過ごしやすい初期症状から、検査のタイミング、広島市内で受けられる検査施設まで、この記事では梅毒に関する重要な情報をお伝えします。
自分自身や大切な人の健康を守るために、梅毒の初期症状と検査の必要性について正しい知識を身につけましょう。広島ウェルネスクリニックでは、プライバシーに配慮した性感染症検査を提供しています。不安な症状がある方、心配事がある方は、ぜひ専門医にご相談ください。
1. 【保健所でも検査可能】梅毒の初期症状と見逃しやすいサイン:専門医が解説する早期発見のポイント
梅毒は近年感染者数が急増している性感染症です。初期症状が軽微であったり、自然に消失したりすることから見逃されやすく、そのまま放置すると重篤な合併症を引き起こす恐れがあります。梅毒の初期症状の多くは感染から約3週間後に現れ、最も特徴的な症状は「初期硬結」と呼ばれる無痛性の潰瘍やしこりです。これは陰部や口腔内、肛門周囲などに現れますが、痛みを伴わないため気づかないことも少なくありません。
また、感染から6〜8週間後には、全身に赤褐色の発疹が現れる第二期梅毒に進行することがあります。この発疹は手のひらや足の裏にも現れるのが特徴で、発熱、倦怠感、リンパ節の腫れなどを伴うこともあります。しかし、これらの症状も自然に消失するため、病気が治ったと誤解されがちです。
梅毒検査は多くの保健所で無料・匿名で受けることができます。東京都新宿区の東新宿保健センターや大阪市北区の大阪市保健所など、全国の保健所では定期的に検査日を設けています。また、性病科や泌尿器科などの医療機関でも保険適用で検査が可能です。早期発見・早期治療により、抗生物質の投与で完治する可能性が高まるため、リスクのある行為があった場合や不安がある場合は、迷わず検査を受けることが重要です。
2. 梅毒感染者が過去最多を更新:初期症状から検査までの全知識と広島での検査体制
梅毒感染者数が日本全国で急増しており、過去最多を記録しています。特に20代から40代の感染者が目立っており、性感染症への警戒が必要な状況です。梅毒は初期症状が軽微なため見過ごされがちですが、適切な検査と早期治療が重要です。
梅毒の初期症状は感染後3〜6週間で現れ、感染部位に無痛性の潰瘍(しこり)ができることが特徴です。この初期症状は自然に消えるため、感染に気づかないまま病気が進行するケースが多くあります。第二期には全身に赤い発疹が出現し、特に手のひらや足の裏に現れることが特徴的です。発熱やリンパ節の腫れを伴うこともあります。
検査は血液検査が一般的で、感染初期には偽陰性の可能性もあるため、感染の可能性がある行為から6週間以上経過してからの検査が推奨されています。広島市では保健センターで無料・匿名の梅毒検査を実施しており、予約制で受けることができます。広島県内の他の地域でも各保健所で同様のサービスを提供しています。
梅毒は早期発見・早期治療が可能な感染症です。ペニシリン系抗生物質による治療が有効で、初期段階であれば完治が期待できます。しかし、治療が遅れると心臓や脳などの重要な臓器に深刻な合併症を引き起こす可能性があります。
不特定多数との性的接触がある方、パートナーに感染の疑いがある方、または症状に心当たりがある方は、迷わず検査を受けることが重要です。広島市中区の広島市保健所や南区の広島市南保健センターなどで検査を受けることができます。また、プライバシーを重視する場合は、広島市内の一部のクリニックでも自費検査が可能です。
3. 気づかないうちに進行する危険:梅毒の初期症状と適切な検査時期について知っておくべきこと
梅毒の初期症状はしばしば軽微で見落とされがちです。感染から約3週間後に現れる第一期梅毒では、感染部位に無痛性の硬い潰瘍(しこり)が形成されます。これは「硬性下疳(こうせいげかん)」と呼ばれ、性器や口腔内、肛門周辺などに現れますが、痛みがないため気づかないことも多いのです。この初期症状は自然に消えるため、治療せずに放置してしまう方が少なくありません。
第二期梅毒は感染から6週間〜6ヶ月後に発症し、全身に赤い発疹が広がります。特に手のひらや足の裏に現れるのが特徴的です。また、発熱、倦怠感、リンパ節の腫れなどのインフルエンザに似た症状も伴います。これらの症状も2〜10週間で自然に消失するため、「治った」と誤解されることがあります。
しかし実際には、梅毒は体内で潜伏し続け、放置すると第三期、第四期へと進行します。神経系や心血管系に重大な障害をもたらす可能性があり、最悪の場合、死に至ることもあります。また、妊婦が感染すると胎児に先天性梅毒が引き起こされる危険性もあります。
検査のタイミングとしては、感染リスクのある行為から3〜4週間後が最適です。検査方法には血液検査が一般的で、RPR法やTP抗体検査などが用いられます。国立国際医療研究センターや各地の保健所では匿名・無料で検査を受けることができます。民間のクリニックでも保険適用で検査が可能です。
梅毒は早期発見・早期治療が重要です。初期であればペニシリン系抗生物質による治療で完治する可能性が高くなります。症状がなくても感染リスクがあった場合は、必ず検査を受けることをお勧めします。自分自身と大切な人を守るために、梅毒の初期症状と適切な検査時期について正しい知識を持ちましょう。


